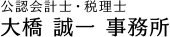1.平成27年〇月〇日
朝にPCを開けたらリモートコントロールがどうこうという表示が現れる。
A審査官に聞いたら「誰かから閲覧されているということでは?」と言われる。
3役打ち合わせ後に部長の時間が限られるということで、終了後「今からどうですか?」
と言われたが、A審査官はそれを想定していなかったようで、11:30開始にしてもらう。
1時間以上猶予ができたことで、自分は検討会の手控えを作成する。
開始10分前になってもA審査官から手直しの議決書が出て来ず、もうぶっつけ本番になるが、A審査官は11:30になっていることに気が付いていなかったようだ。
午後に明日の研修の配置設定をすることについて、審査官に招集がかかる。
部長説明では、手控えを基に説明していたが、なかなかA審査官がフォローに入ってくれず、苦しくなってしどろもどろ気味になってきたところで、フォローに入ってくれた。
後で聞くと、「説明がすごいわかりやすかった。」と言われたので、フォローする必要がないと思っていたらしい・・・なんだ。
部長は、「・・・」「・・・」「・・・性質の事件だろう。」ということで了となりだが、証拠(目録)をどうつけるかという話になった。
終了後、主任審判官を交えて証拠関係の話をしたが、・・・ことは現実的でないし、いくつか主要な箇所の証拠を添付しようかということになった。
2.研修準備
お昼は、部長と主任審判官とA審査官と4人で行く。
B事件の代理人に電話をしてもらうようお願いしていたが、「・・・」と言っていたので「えっ!」と身構えたら、「・・・で。」と言われたところ、B審査官が「その場合でも・・・。」と切り返してくれ、「ならば・・・」ということで、1週間延長となった。
副審判官が、「A事件の部長説明の後に、E事件の打ち合わせの時間を。」と主任審判官に依頼し、午後一番から第3合議室で打ち合わせをしていたようだが、B審査官も入ったので、明日の研修の15階の設営には参加しなかったようだ。
総括審判官も、1人足らないのであれば自分に声をかけてくれてもよいのだが、そこは上下関係というところだろう。
京都支所ハイキングの出欠回覧が来たが、部長は出席で、1部門は全員不参加、2部門は全員参加となっていた。
明日の研修は、主任審判官は所長講話しか受けられないので、携帯録音機を管理課から借りて、所長講話後の講義を録音してもらうようにA審査官に依頼していた。
I事件のファイルをもらうが、管理課が聞いた話では総代を選任しないようだ。
その場合は通則法108条2項で国税不服審判所長は互選命令が出せる旨の規定があるが。
請求人は「・・・」という主張をしているように見えるが、何せ審査請求書が異議決定書のべ夕打ちを含めて18頁もあり、これが正しい理解かどうか自信がない。
「・・・」「・・・」「・・・」などの疑問が生ずる。
いずれにしても、主張はともかく、審査請求書をみるにつけ、この・・・は相当気になるところである。
6時過ぎになって、A審査官が、「今日はA事件の起案はもうしませんよ。」と言われるが、それで間に合うのかなあと思いつつ、依拠してしまう。
I事件の審査請求書について「意味がわからない。」と言い続けているB審査官を残して退所する。