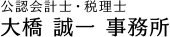1.総額主義とは
税務争訟における被告(国)の主張に関連する重要な問題に、総額主義と争点主義の対立があります。
通説によれば、課税処分取消訴訟の訴訟物は、他の行政処分取消訴訟のそれと同じく、処分の違法性一般(処分の主体、内容、手続、方式等全ての面における違法)であるとされており、最高裁判例も課税処分取消訴訟の訴訟物は、課税処分の違法一般であると判示しています。
しかし、この通説の立場に立っても、処分の同一性をどう捉えるかによって、訴訟物(審理の対象)が異なってきます。
総額主義は、課税処分の同一性を、それによって確定される租税債務の同一性によって捉える考え方をいい、例えば、特定人の特定年分の所得税ということで、その課税処分の同一性を捉えることになります。
もちろん、租税債務を確定するには、事実上の基礎と法律上の根拠、すなわち処分理由が存しなければなりません。
この処分理由については、「処分時に客観的に存した理由」という捉え方と、「税務署長が現実に認定した理由」という捉え方の二つがあり得るところですが、総額主義は、課税処分の同一性を上記のように捉えることと併せて、処分理由についても、「処分時に客観的に存した(本来あるべき)理由」という捉え方をすることになります。
このようにして、総額主義は、課税処分によって確定された税額(租税債務の内容)が総額において租税実体法によって客観的に定まっている(本来あるべきだった)税額を超えていなければ、その課税処分は適法であると考えることになります。
すなわち、課税処分において税務署長がいかなる理由で税額を認定したかは別として、結論としての数額が処分時に客観的に存在した(本来あるべきだった)税額を上回らなければ(換言すれば、上記の客観的処分理由の存在が肯定されれば)、違法に納税義務を重課したことにはならず、処分は適法と考えることになります。
したがって、審理の範囲は、課税処分によって確定された税額が総額において処分時に客観的に存した(本来あるべき)税額を上回るか否かを判断するに必要な事項の全部に及ぶことになります。
そうすると、その数額の計算の根拠となる事実は単なる攻撃防御の方法にすぎず、税務署長は、処分時の認定理由に拘束されることなく、訴訟の段階で、その後に新たに発見した事実を追加し、あるいは上記事実と交換することによって、処分理由を差し替えることが可能であり、その課税処分に係る税額の数額を維持するため一切の理由を訴訟において主張することができることになります。
このように、課税処分によって確定された税額が客観的な(本来あるべきであった)税額を超えるか否かを審理し、判決でその課税処分を取り消すことになると、判決は税務署長が一定額を超えて税額を認定したことが違法である(換言すれば、一定額を超えては客観的処分理由が存在しない。)と判断したことになるため、判決の拘束力により、税務署長は訴訟で主張しなかった理由をもってしても、上記の額を超える課税処分を再度行うことができないことになります。
その効果として、総額主義によれば、紛争の一回的解決が図られる(蒸し返しされない)ことになります。
2.争点主義
これに対し、争点主義は、「処分理由について税務署長が処分時に現実に認定した理由」という捉え方をした上で、課税処分の同一性を上記処分理由の同一性によって捉えることにより、課税処分取消訴訟の審理の対象は上記処分理由との関係における税額の適否であるとする考え方をいいます。
そして、税務署長が処分時に認定した理由が誤っていれば、他に所得等があり、客観的な(本来あるべきであった)税額が数額において課税処分で認定されたそれを上回っていても、その課税処分は違法として取消しを免れないことになります。
したがって、審理の範囲は、処分時の認定理由の存否に限定されることになり、それのみを争点として審理が行われるのであって、訴訟の段階で処分理由を差し替えることは許されません。
その代わりとして、判決でその課税処分を違法と判断しても、その違法判断は税務署長が処分時に現実に認定した理由にのみ係るものであり、更正・決定の除斥期問内であれば、新たな理由に基づいて再更正をすることも許容されることになります。
争点主義の代表的な考え方は文化勲章受章者である金子宏教授の見解にみることができます。
「法が一般的に理由の記載を要求している理由は、1つには、手続的保障の見地から、処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制する(処分適正化機能)とともに、処分の理由を示して、不服申立に便宜を与える(争点明確化機能)ことにあるが、理由の差替を自由に認めることは、理由を記載しないで処分を行うのと結果的に同じことであり、せっかく理由の記載を要求した法の趣旨の大半を失わせることになりかねない。
その意味では、租税争訟の審理の対象ないし訴訟物は処分理由との関係における税額の適否であり、理由の差替は原則として認められないと解するのが、法の趣旨に合致しているといえよう。
なお、租税処分に対する取消訴訟の提起には、前述のように、不服申立の前置が要求されているが、その1つの理由は、裁判所の負担を軽減するため、不服申立の段階で事実上・法律上の争点をなるべく整理させた上で出訴を認めることにあるが、理由の差替を認めることは、この点でも問題がある。
もっとも、争点主義をとった場合にも、理由の差替が絶対に認められないと解するのは妥当ではなく、原処分の理由とされた基本的課税要件事実の同一性が失われない範囲では理由の差替は認められると解すべきである。」
このように、争点主義は、手続的保障の面では利点がありますが、紛争の一回的解決が図られない(別の論点があれば、その論点で再度審理が開始される可能性がある)という難点があります。
3.判例の考え方
判例は総額主義を採用しており、以下のように判示しています。
「課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は、その課税処分によって確定された税額の適否であり、課税処分における税務署長の所得の源泉の認定等に誤りがあっても、これにより確定された税額が総額において租税法規によって客観的に定まっている税額を上回らなければ、その課税処分は適法というべきである。」
国税通則法24条から29条等の規定からすれば、課税処分はその年又は年度分の課税標準等又は税額等を数額的に確定させる処分であり、それが数額的に過少又は過大である場合にのみ行うものであって、数額算定の根拠事実が異なる場合に行うものではないと解されます。
そうすると、課税処分の同一性は、それによって確定される租税債務の同一性によって捉えるという考え方が相当となり、総額主義が妥当することになります。
ただし、訴訟の段階で無条件に処分理由の差替えを認めてよいかについては、手続的保障の面から別途考慮が必要でしょう。
すなわち、処分理由と訴訟において被告(国)が主張する理由との間に、基本的な課税要件事実の同一性があり、原告(納税者)の手続的権利に格別の支障がないと認められるような場合に限って、理由の差替えを認めるべきでしょう。
4.国税不服審査と総額主義・争点主義
総額主義・争点主義は、課税処分取消訴訟の訴訟物に関して論点となりますが、これとは別に、国税の不服審査を行う審査庁の審理の範囲に関して、総額主義・争点主義が議論されることがありますが、この問題は、審査庁の審理の範囲がどこまで及ぶかということです。
不服申立てにおいて、総額主義とは、審査庁の審理の範囲は原処分によって認定された所得金額全体の当否に及ぶという考え方であるのに対して、争点主義とは、上記の審理の範囲は原処分の認定額のうち不服申立てに係る争点事項とこれに密接に関連する事項に限定され、これを争点として審理されるという考え方をいいます。
両者の考え方の相違は、基本的には、国税不服審査手続を全体として職権主義的に理解するか、あるいは当事者主義的に理解するかということであり、具体的には国税通則法の関係規定をどのように解釈するかによります。
しかし、国税通則法には民事訴訟法246条(判決事項)のような明文の規定がないほか、納税者と課税庁という両当事者対等の審理構造が採用されておらず、審査庁が主導的な立場で事案の調査、探知に当たることが予定されていることを考えると、国税通則法は総額主義を採用しているものと解されます。
この点、判例は総額主義を採用しており、審査手続における審査の範囲に関して以下のように判示しています。
「本件決定処分は、上告人の昭和38年における総所得金額に対する課税処分であるから、その審査手続における審査の範囲も、右総所得金額に対する課税の当否を判断するに必要な事項全般に及ぶものというべきであり、したがって、本件審査裁決が・・・給与所得の金額を新たに認定してこれを考慮のうえ審査請求を棄却したことには、所論の違法があるとはいえない。」
もっとも、国税不服審判所における審理実務については、理論上は総額主義を前提として原処分の認定額全体の当否を審理することになるものの、その判断は、原則として争点及び争点関連事項に係る審査庁の調査資料並びに争点外事項に係る原処分庁の調査資料に基づいて行うとの審理方針(争点主義的運営)が確立しています。