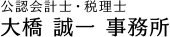1.平成27年〇月〇日
回覧が回ってくるが、納税協会の会報に自分と入れ替わりで卒業した税理士出身審判官の連載が載っている。
弁護士出身審判官が、「同席主張説明で審理課職員を原処分庁が同席させたときに、認める(断る)法令根拠はあるか。」と聞かれたが、財務省設置法による「指導・監督」では根拠としては緩く、担当審判官の裁量という現在の整理から、改正後は認めないとの方向になるようだ。
ただ、その場合の原処分庁側の対策としては併任をかけるということになるようだ。
本来、原処分庁とは関係のない職員を同席させるのはどうかと思うが、現時点では「事件進行の円滑はむしろ請求人にとっても良い。」との整理をしているようだ。
次席面談については、その前の主任審判官が20分と長かったが、自分は10分程度で終了した。
初めて次席室に入ったが、南側はやはり熱い感じだ。
内容は「延長希望ということだが」ということから始まったが、「最後の1年が縁もゆかりもない地域になることは基本的にはないのではないか?(都市部出身で地方に配属された方の3年目で配慮があるように)」とのことであった。
後は、「任官終了後どうしようと思っているのか。」についてと、「会計士だけの出身者は苦労するけど、あなたは税理士経由であるのでその点では苦労は少ないのではないか。徴収はなじみがないと思うけど。」という話だった。
主任審判官のように管理の話がないせいか、最低限の時間で終了した感じだ。
2.求釈明事項のすり合わせ
I事件の求釈明質問事項については、11時から第3合議室でセッティングさせてもらう。
午前で終了するかと思いきや、「・・・ことの求釈明はその他の質問でさらっとすれば?」「・・・などの質問事項については課税要件に関係がないのでなくてもよい。」などの意見が出て午後に持ち越しになった。
午後にも話が及ぶが、主任審判官から「・・・について求釈明しなくても良いのか。」という問題提起があったが、弁護士出身審判官が「・・・場合には、・・・はないのでは?そうしないと・・・。」と答えてくれた。
副審判官からは、「・・・」という問題提起があったが、そこは・・・という点で関係があるということを話した。
結局、・・・という3点で送ることになった。
審理部審理部のA副審判官がやってきて、A事件は所長の年内最終決裁に滑り込ませたい(年初からは1部門のI事件事件にシフトするつもり)と思うので、議決は年内で議決説明会を省略して問に合わせたいという話があったが、自分としては、議決説明会の省略は願ったりかなったりである。
任期付の全国研修会が・・・月に都内で開催されるとの案内が東京支部の任期付審判官からあるが、おそらく今回も欠席だろう。
回覧されていた税務雑誌に平成21年から4年間任期付審判官だった弁護士の坂田真吾さんの論文があったが、添付されていた当時の職員録によると、当時の2部は16人もいたのかと思い、人員削減がじわじわされていることを感じる。
I事件の釈明陳述録取書の手直しに入るが、その途中で定時になる。
また、弁護士出身審判官のところに制度改正関係の意見聴取依頼が来ているようであり、来週回覧されるようである。
3.事件のモデル処理期間
1部の総括審判官が弁護士出身審判官のところに来て、17時を過ぎても弁護士出身審判官が残っているので、おそらく元支所関係の飲み会なのだろう。
主任審判官が、I事件で「・・・がアキレス腱になりはしないか。」と言ってきた。
・・・ので、今(審査請求)となっては心配なのだろうが、原処分担当者としては酷なのではないかと思う。
定時を過ぎるが、昨日の1部の・・・事件の裁決書を確認してから退所することにする。
総括審判官が、C事件の進行管理表の「請求人面談、同席同時実施」の記載を見て、「意味がわからん。同席主張説明実施と変えてくれ。」と主任審判官に言いに来た。
A審査官が証拠番号を打っているが、ボリューム的にはB事件かC事件であろう。
来週の本部次長視察の際に、長期議決未済事件にっいての報告をしないといけないようで、B審査官が内容を弁護士出身審判官に報告していた。
G事件のD事件モデル期間経過が・・・月・・・日であり、B審査官が「過ぎたんですね。」とぼそっと言った。
B審査官が、・・・の判例を見ているようだが、過去に、・・・を争点とする主張で「・・・」という主張があったようであるが、何でも主張すれば良いというものでもないだろう。