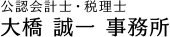1.平成27年〇月〇日
第1部の部長、総括審判官、主任審判官が挨拶に来て、自分の所属する部門の主任審判官が「飲みすぎた。」と言っていたので、1部と2部の3役同士で飲み会があったのだろう。
A審査官が明日休みなので、口頭意見陳述及び争点の確認表その後の打ち合わせを今日したいところである。
弁護士出身審判官にA事件の事件ファイルがB審査官から配付された。
争点の確認表については、現在のA審査官の議決書案ベースで書き換える(というか貼りかえる)。
B審査官が、「異議決定で一部取消しとなった場合に、審査請求書で『原処分の全部の取消し』を求めていると書いてあると補正してもらう必要があるのか?」と聞いていたが、A審査官も「?」ということで、2人で調べている。
意を決してB事件の口頭意見陳述関係の話をしたが、弁護士出身審判官に、発言者が複数あったときに、発言者ごとに内容の特定をしないといけないのではないか、その場合はどうするか?というコメントがあった。
その場合は、「この部分は甲さん、その部分は乙さん」として録取書を作成するしかないようだが、要旨から外れたことを言った場合(特に本人)には、「時間に制約がありこの場でまとめられないので、そちらでご相談いただいて、主張される場合は別途書面を提出してください。」というようにしよう、ということになった。
弁護士出身審判官からは、「事前に提出された陳述要旨に少しでもこだわる場合は、要旨添付の録取書にする。まったくこだわらない場合は別途書面を提出させる。」というスタンスでいけば?というアドバイスをもらう。
主任審判官が、A審査官に「B事件はいつごろ打ち合わせする?」とさらっと聞いてくれた!・・・嬉しい!
A審査官としては〇日以後希望ということで、〇~〇日に合議体打ち合わせ、翌週始めに部長説明、主任審判官が対応できる〇日までに実質仕上げて〇日配付というスケジュールでいきましょうかということになった。
2.審理留保の見込み
A審査官が、所内のシステム関係で会計係の主任の相談を受けている。
総務第一係の主任から監察官室リーフレットがメール添付で来るが、情報漏洩に関する内容であり、概要は、「つぷやく(SNS)」「なくす(紛失)」「話す」はダメ!ということである。
午前においてはA事件の答弁書は来なかったが、もしかして、「水曜日発送します。」というのは、「私(異議担当者)の手許を離れます。」という意味であって、郵便局への持ち込みが水曜日であるとは限らないのかもしれない・・・そうなったら完全に来週になってしまうし、火曜日はバタバタするので水曜日になってしまうかも。
昼休みは、A審査官と「第2部の互助会である『二審会』の会費はどこに消えている?そもそも帳簿はどこにある?」みたいな話から神戸支所の時の話をしていた。
午後一番にC事件の関係の訴訟の次回の期日は〇月〇日ということの連絡があった。
証拠調べは早くて〇月、判決は〇月・・・とかになるともう弁護士出身審判官では処理は無理だろう。
「引継書書いときますわ。」と冗談で言われる。
3.調査関係資料は生々しい
予定通りA事件の答弁書が出てきたが、通則法96条任意提出証拠で10㎝以上の分厚さがあった。
ほとんどが調査報告書であり、少し読んだが、原処分調査の生々しさを感じる。
さっそく担当審判官決裁等を起案してもらい、部長決裁までは了する。
答弁書と異議決定書の比較をするが、一応審査請求書に記載の個々の理由については答えてくれている。
「総括審判官が、・・・対応マニュアルがあったはずと言っていた。」と主任審判官が言っていたが。A審査官は知らないようだ。
「そのマニュアルとやらは一子相伝では?口述筆記で稗田阿礼が太安万侶に書かせていたりして」と言ったら思いのほか受けた・・・みんな教養があるというか公務員試験に出るのかな。
改めてA事件の調査記録を読み続けるが、生々しいというか税務職員も大変だなと思う。
答弁書との整合をみると、異議決定書が誤っていた点が1つ、調査報告書と違う点が1点、調査報告書がないのが2点あるように感じたので、明日B審査官か副審判官に見てもらうとともに、合議資料を修正していこうと思う。