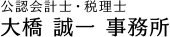1.平成27年〇月〇日
配偶者が出産間近で休暇を取得しているB審査官から「生まれました!」の連絡がないな~と主任審判官が心配している。
午後になってメールが来たようだが、まだ生まれていないそうで、今週はただ年次休暇を消化しただけだったようだ。
審判所長による裁決が追加になっているが、更正理由不備を争った事案であり、「不利益処分をすることの手続の慎重さと恣意の抑制」「不服申立ての便宜」を満たしていれば十分という従来の法令解釈で判断できる事案である。
先日裁決が出てまだ確認できていない・・・による更正・重課事案(理由付記・手続違法・偽りその他不正の行為・隠ぺい仮装)についても今日確認しておこう。
A事件の事件検討会につき、〇日は次席審判官の都合が悪くなったということで、1部門の事件と併せてということになり、「議決書案と事件検討会資料作りの余裕ができた~。」とA審査官が喜んでいたが、「〇日時点の議決書案を部長に事前に入れるように」と言われ、「え~!結局仕事増えるじゃん」と言っている。
ただ、「だいぶ自分の頭の中でイメージができてきた」とも言っていて、しばらくは自分があまり口出ししない方が良いようだ。
1部門のC事件より2部門の自分の担当するA事件の方が、時間が短いだろうということで、当初「A事件:10:00~10:45」「C事件:11:00~12:00」としていたが、総括審判官が、「45分は短いのでは?次席審判官が出席するのに早く終わりたいことが見え見えではないか?」ということで、「A事件:9:30~10:30」「C事件:10:45~12:00」で落ち着いた。
今日もなぜか部長・総括・主任による3役の打ち合わせは長く1時間以上過ぎても出てこない。
やっと出てきて、「不服申立制度改正によって職権調査収集資料も閲覧謄写対象となることから、証拠資料を収集しすぎないようにしないといけないが、難しいね。」みたいな話を出してきたので、次席審判官あたりがそんな話をしたのかもしれない。
2.審査請求人に危機感がない
昼休みに国税庁舎1階ロビーに自動車保険の代理店の担当者に来てもらって手続をするが、公務員の団体割引は25%で、通常のディーラーの代理店では太刀打ちできないらしい。
昼休みに、副審判官とA審査官が、A審査官の双子の男の子の誕生前後の話をしている。
A審査官が、B事件の請求人の業務内容の調査で請求人本社に行くがそう遠くないようだ。
審理部のC審査官がやってきて、A事件の事件検討会の日程変更を了解した旨を連絡してきた。
D事件の原処分庁から答弁書関係の電話を受け、「答弁書記載の資料は国税通則法96条証拠として提出しますとお伝えください」と言われたので、A事件の事件検討会の日程変更を含めて担当審判官である弁護士出身審判官にメールした。
午後3時直前にB事件の調査に出かけた3人が帰ってきたが、特に1部門の弁護士出身審判官がプンプンしている。
どうやら、審査請求人である向こうに当事者としての危機感がない(準備もしていない)ようで、ほとんど何の成果もなかったそうである。
午後3時の体操をしている間も、1部門の弁護士出身審判官のプンプンにみんな苦笑いしている。
本所全体の予定表を見ると、〇日に近畿税理士会右京支部の研修会が入っていたが、どうやら京都支所長が派遣されるようである。
右京支部は、自分が研修委員長に「不服申立制度の改正のコマを設けてくれるように」と依頼していたのに、なんか手柄を横取りされた感じだ。
3.部長審判官会議の意見徴収
自分が担当することになるE事件の税務調査時の状況が非常に分かりづらいので、ひとつひとつ読みながら表にしてまとめた。
副審判官が事件検討表の書き方について困っていたので、自分のE事件の一部を渡す。
F事件について、主任審判官と副審判官が徴収法75条(差押禁止財産)関係で「商品と製品の区別ってなんだ?」と言っているので公認会計士出身として解説した。
裁決書のWORD様式で、主文のデフォルトが「棄却する。」となっているのが審判所が棄却を前提としているようで違和感があると話していたら、A審査官が「自分が作成したけどそんなことにしてたっけ?」と言って探したら、総務係長がそのように加工していたらしい。
確かに棄却の割合が多いから、今はそんな違和感もなくなってしまったが・・・。
総括審判官が、部長審判官会議の意見聴取について、来週出勤する主任審判官と自分に考えるように依頼を受けた。
他の人は連休明けにしないといけないので免除というわけではないが、来週の静かな間にたくさん意見を出してくれということのようだ。
ファイルを見ると、審査事務提要の案が2メガバイトで来ていた。
開けると77頁もあり、「こんなの逐一チェックしているのは審判所歴が長い神戸支所長くらいじゃないか。」と思った。