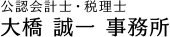1.平成27年○月○日
・・・の12月号に・・・先生の寄稿が載っていたが、・・・と批判している。
B事件も、結局のところ・・・に終局してしまいそうで、・・・どうなるかわからない。
A審査官が、コピーをみつけて話をしてきたので、内容の話をしようとしたら、内容よりも、「この顔どこかでみたことある。」というだけだった。
A事件について改めて・・・を配って合議体で話をして・・・という話になったが、「・・・した方が良いよね。(大変だからね。)」という流れになる。
総括審判官、主任審判官、1部門の副審判官という珍しい打ち合わせをしており、その後、副審判官とB審査官が呼ばれたので何かと思ったら、「・・・の意向で、当初合議前に原処分庁に行って証拠リストを見て、それを当初合議資料につけて合議を充実させること。その後その資料を採りに行く(もしくは送ってもらう)ということになるので、その段取りで原処分庁に打診するなり合議日程を調整するなりするように。」という話だった。
1部門の副審判官主担の事件と、2部門の副審判官主担の事件の2件を試行的にすることになったようだが、後者は担当審判官指定後になるも、前者は答弁書要求中なので、担当審判官が指定されていないのに行く資格があるの?と思ってしまう。
I事件の求釈明方針などについて打ち合わせをしたが、・・・であれば簡単に棄却になるも、・・・である場合には展開が変わることになる。
支所の弁護士出身審判官から丁重なメールが帰ってくる(「前任であるあなたの職権調査や知見は大変参考になりました」的な内容)が、自分としては単に議決書案の修正の過程が見たかっただけなのだが。
2.異体字
A事件の住民票が帰って来たが、名前が異体字だった。
外字登録もされていないので登録してもらわないといけないが、B審査官としては、そもそも本人に補正してもらわなければならないじゃないか(そんなの常識じゃないか?)という認識だったらしく、同じ部門の国税プロパー職員から「そんなの気にしなくて最後に住民票通りに議決書を作成すれば良いのではないの?」と言われて「ツイッターで呟きたいくらい」というほど信じられない様子だった。
B審査官が、総括審判官のいう「一統官」の意味がわからなくてA審査官に聞いていたが、それは大阪局のみらしく、それ以外は「一統括」らしい。
ほかにも、「総長」は、大阪局は総務課長だが、他では総務係長らしい。
B事件の最終合議日程について協議して、最終合議を実際に開催するかどうかを審理部と相談したら?ということになったが、合議資料(議決書案)がいつできるかにもよる。
明日のハイキングは雨天中止になる。
予防講話の前に支所の弁護士出身審判官に声をかけられるが、支所で引き継いだF事件について、未済事件説明会における所長・次席審判官の指示・コメントについて質問された。
・・・について税理士としての感覚を聞かれたが、まだ方向性が決まっていないんだろうと思う。
3.監察官講話
監察官講話は、主任監察官の説明と「心の隙間<自覚とモラル>」という監察官室DVDの視聴と主席監察官講話の3本立てで、最後に一昨日受講できなかった局長講話の内容を言われる。
大阪局は・・・なのだそうだ。
局長が予防講話で自ら話すことは全国でも初めてのことで、それだけ危機感は強いようだ。
局長は、「一般納税者からそっぽを向かれるとボディブローのように効いてくる」「経験則は過信するな。」という話をしていたようだ。
1部門の弁護士出身審判官が、最後尾であることを良いことに・・・をしていて、最後の局長講話部分はうとうとしていた。
I事件につき本部から回答があったようだが、・・・で主文は・・・との回答だった。
そうなるともっとも簡単なパターンになるが、A審査官が「本当にそれで良いの?」と腑に落ちない感じである。
1部門の弁護士出身審判官を、1部2部門と管理係の審査官が迎えにきたが、女性陣の飲み会なのか。
去年の(12月給与の前に支給される)期末手当段階で年末調整をしていたのを不思議に思っていたことをA審査官に言うと、12月給与が2回ある場合は初回の方で調整してもよいという取扱いがあるから(でも結局最終給与でも年末調整している)と教えてくれた。