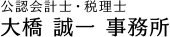1.平成27年○月○日
B審査官によると、裁判所は・・・に評価をつけているという。
しかし、評価と業務の向き不向きは必ずしも一致していないという。
B事件の争点の確認表と審理の状況予定表の決裁が回ってくるが、前者の期限が19日、後者が18日になっていることを指摘すると、そもそも、後者は期限を決めてコメントする性質のものではなく、削除して再度決裁が回ってきた・・・そこまで見ていなかったが。
主任審判官は、午後からの近畿税理士会田辺支部の国税不服申立制度の改正説明会で、3役打ち合わせ後、10時頃に早々に出るが、部長は、「B事件の議決説明会の省略時にどのような書面を差し入れるのか?」という疑問を持ったようである。
議決説明会の位置づけは、瀧華さんより前の審判所長の時代は「お疲れ様。これからは審理部の仕切りで直しますよ。」という場だったが、神戸支所に居るとよくわからなかったが、瀧華さんは、内容によっては差戻しになるので、この場でしっかり議論しなければという立場だったらしい。
現在の黒野所長は、元に戻ったような考えらしく、そうなると、事件検討会までした事件の議決説明会の位置づけはかなり低くなるが、部長としては管理課長の経験から、「本来やることになっている手続をやらないというのは何か事情説明が居るのではないか?」という疑問を持っているらしい。
A審査官に争点の確認表を部長に入れてもらったときに説明してもらう。
2.支部内・審判部内の統一感
A審査官が、主任審判官に、「2部は審理の状況予定表を送らない伝統がある。」と言っていて、確かに神戸支所のときも「なぜ3か月接触なしで送付するとしていながら議決段階に送るのだろう?」と思っていたが、支部内だけではなく部内の統一感もなく、さっぱり理解できない。
年末調整のシステムデータ入力を行うが、2回目ということもあってかすぐ終わる。
徴収の新件につき、管理係審査官から総括審判官が引き渡しを受けていたが、後で「昼からもう1件くるから一緒に配付するか。」と庶務担当審査官に話している。
結局2件とも1部門になるようだが、2件ともそんなに重くはないらしく、軽い事案は1部門で2部門がディープな事案(次は自分に配付されるだろう)が来たらいやだな~。
審判官対象に近畿税理士会の名簿が配付されたが、自分は本会からも来るので、副審判官に謹呈するが、迷惑だったかも。
3.引き継いだ事案の裁決
総括審判官が、12月4日午後に本部の部長審判官が視察に来るが、自分とA審査官が2部からの意見交換会出席メンバーとして予定しているので予定を空けておくようにと言われる。
午後になって、神戸で神戸支所の弁護士出身審判官に引き継いだE事件の見え消しが出ていることに気付くが、判断部分がかなりすっきりしていて、自分が神戸支所の弁護士出身審判官にどんな議決書案を引き継いだのか思い出せないほどである。
昨日のI事件の原処分庁調査については、・・・ところに両者の主張の食い違いがあるようだ。
A審査官が、B事件の一件書類の整理に入っているが、前合議体の書類が無駄に多く、96条証拠と97条証拠の重複も多く、途方に暮れていた。
B審査官に「・・・か?」と話を振ったが、「・・・ではないか?」と言われる・・・実際には・・・もないのだが、議決書案を「・・・論」で修正する。
審理部のA副審判官とA審査官が、I事件で識論しているが、先はどの主張の食い違いをA審査官が説明していた。
ハイキングの担当者が総務係の主任に変更されていたが、会計長が急遽ハイキングに参加できないかもしれない。
B審査官に、「A事件で・・・はどこにありましたっけ?」と聞き、裁決では・・・があるとは言われたが、判決については正面からではないものの・・・が参考になるそうだ。
主任審判官からA審査官に午後3時過ぎに「直帰します」という連絡があった。